全日本きもの装いコンテストは、1972年(昭和47年)に第一回が東京帝国劇場にて開催されて以来,40年以上にわたり続いている日本有数の権威ある,きものコンテストです。

表彰台左端が中井川教諭

ご指導いただいている鈴木よし子先生と
夏休み、過ぎてしまうとあっという間ですね。4月から石岡二高勤務になり半年が過ぎようとしています。女子が7割いる学校はどんなだろうと思いつつも、時は平穏に過ぎていきました。とても居心地のよい学校で、久々に学校に来るのが楽しみな毎日です。
さて、今回は夏休みの思い出について思うままに語ってみたいと思います。
3年前、山登りに挑戦しました。最初は体調管理のために始めたwalkingでしたが、ちょっと欲が出て無謀にも挑戦した山がマッターホルン。3000m付近までのトレッキングでしたが、準備をしたとはいえ、普段何もしていなかった私には過ぎた挑戦でした。おっかなびっくりで挑戦したために、あと一歩の冒険ができなかったことが心残りでした。そしてその残念な思いを払拭するために、今年再挑戦をしたのです。相変わらず怠け者生活で、すっかりだめな体になっていたのを1ヶ月かけてトレーニングしました。はじめはただ歩くだけ、そのうち負荷をかけるようになり、出発前には20kgのリュックを背負い、校舎の4階までを休まずに11往復できるまでになりました。加えて夜にはマウンティングバイクに乗って坂の上り下りもしました。ま、自分なりに前回よりも準備ができたという自負ができての挑戦でした。強風の日が続いたこともあり、麓の街ツェルマットに着いてから4日目の挑戦でした。前回挑戦したコースの再挑戦でした。ですが、3000m付近まで登った時に、トレーニングの成果からか前回よりも体が動いている自分にうれしさを感じていました。このことが後の後悔につながるのですが、無計画の私はそのときの気分まかせで、途中でコース変更してしまい、なんとマニアでも7.5時間かかるコースに進んで行ったのです。途中で引き返そうと思ったのも事実ですが、もう行くしかないと思い、後はひたすら前進あるのみ。崖の上を歩くのが続いた場所では、高所恐怖症の私は薄目を開けての踏破でした。映画「八甲田山」の場面が何度頭に浮かんだことか。常に頭の中でリハーサルをして「倒れるときには山側」これを念仏のように唱えていました。ホテルを出て10時間、ボロ切れのようになってやっと帰ってきて、泥のように眠って(泥睡)してしまいました。私の訪れた今年のヨーロッパ(スイス・フランス・ドイツ)はとても涼しく、パリで挑戦した4時間のサイクリングツアーも快適でした。いつの日かまた挑戦したいと思っています。では!






2つ目は顧問をしているバドミントン部を県ベスト8に入れることです。3年前は部員4名で団体戦に出るのもやっとの状態でしたが,今では男女合わせて19名で活動しています。今年度の関東大会県予選では男子団体で県ベスト16に入ることができました。3年生も引退し,また一からのスタートですが,OB・OGが作り上げた部活を少しでも大きく成長させたいと思います。まだまだベスト8に入る実力はありませんが,今後も生徒達には頑張っていただこうと思います。



 えてくれました。
えてくれました。 今年度から石岡二高で養護教諭をしております佐藤公美と申します。
今年度から石岡二高で養護教諭をしております佐藤公美と申します。教員人生1年目、たくさんの先生方や様々な物から学びや刺激を得ると共に、私生活でもゴルフやボルダリングなど新たなものに挑戦をしています。











ほんの数十分の探訪でしたが、新しい発見がたくさんありました。
エッセイという事で,何を書いたら良いものかと考えておりました櫻井です。石岡第二高等学校での生活について,皆様の糧にならないような話です,はい。

朝,筑波山を眺めつつ,鳥たちの生活を盗み見する。特別棟の壁に新居を作り,あんなに大忙しで子育てしていたツバメたちも,気が付いたらお引越し。スズメたちのヒナも,すっかり大きくなり一人前の生活。プールにおいてはいろいろな鳥が水浴び。少し下手だったウグイスもすっかり上手に,シジュウカラはいつも安定した鳴き方で鳴いている。生物室の窓際には,ヘビが脱いでいった抜け殻がきれいに残されている。
昼,高校生の元気な声と,教職員の落ち着いた声を同時に聞きながら。中庭でうろうろしているヘビやトカゲを見かけたときは思わず,そこいるよと立ち止まる。そういえば,ずっと聞こえているのにセミの存在を忘れかけていた。
夕方,コクワガタを玄関で見かける。一度だけ,タマムシの死骸を拾う。素晴らしい造形だと感動する。筑波山が夕日に染まる頃,中庭や小体育館ではコウモリが舞っている。高校生は自分の活動に忙しくてなかなか気が付いていない。それぞれが,それぞれで生命活動している様子を同時に眺められる。
毎日,沢山の生命が活動している。筑波山は四季折々で姿を変えるようでいて,いつもしっかりと存在している。変化する自然と不変の自然。高校生に伝えたいと思うが,残念ながら上手に表現する術を持てないでいる。

渉外部担当の渡邊信人です。校長先生から「リレーエッセイ」のお話はうかがっていましたが、まだ先のこと、と何も考ずにいたら、もう始まっていました。校長先生は行動が早い、そして大崎先生はじめ、若い先生方は反応は早いしペンも早い。先輩として遅れてはならじと重いペンを取ることにしました。
渉外部は、PTAと同窓会に関わる仕事をしています。普段、仕事としてお目にかかるのは、保護者の皆様や同窓会の役員の皆様という大人の方がほとんどです。そのため、生徒にとっては「国語の先生」という認識しかないかもしれませんし、授業に出ていないクラスの生徒にとっては、ただの「おじさん」あるいは「おじいさん」という存在かもしれません。
でも、最近は、「ただのおじいさん」という立ち位置が気に入っています。「好々爺」という言葉がありますが、ストレスフルな現代には必要な存在なのかもしれないなと思います。とは言いながら、なかなか好々爺でばかりもいられません。今年度で退職という先が見えてくると、まだまだ伝えたいことがたくさんあるのに、まだまだ子どもたちに伝え切れていないという焦りも感じてしまうのです。年を取ると気が短くなる、とよく言われますが、それにはきっとこんな焦りもあるのかもしれません。よりよく生きていくためには、こんなこともあんなことも知って欲しい、あれもこれもできるようになって欲しいという思いがあふれてくるのです。
そのようなものの一つに、「社会性」というものがあります。社会は人と人との関わりで成り立っています。性別の違い年齢の違い、性格の違い考え方の違い、いろいろな人と関わって生きていきます。これは学校の中だけでは充分に学ぶことができないものだと思います。そこで、生徒の皆さんに考えて欲しいのは、学校の外に出て、知らなかった人たちと関わり合う機会を持つことです。しかし、突然、知らない人に声をかけたら不審者です。学校で紹介したり募集したりしているボランティアに参加する方が間違いありません。
生徒会で募集するもの、生活デザイン科で募集するものなど様々なものがありますが、私たちが募集しているものとして、「府中小学校・学びの広場サポートボランティア」と「歴史は物語だ!」という二つの活動があります。
「学びの広場」は県内の全小学校で実施されている算数の学習を、府中小学校に出向いて、先生方のお手伝いをするというもので、今年で4年目になります。この夏も、のべ40名ほどの石岡二高生が参加しました。「歴史は物語だ!」は、石岡の歴史を市内の史跡を巡りながら石岡歴史ボランティアの方々から説明を受け、その後は常磐大学の先生や学生と話し合いを重ねながら、歴史を石岡の街興しとして使えないかを考えるという活動です。


これらの活動を通して学んで欲しいのは、様々な人との関わりと地域社会への奉仕の精神です。誰かのために何かをする、一人ではなく皆とする、それは楽しいことなのだという心を育てて欲しいと思うのです。
最近は、教科学習の中にも、「アクティブ・ラーニング」という流れが入ってきています。ものごとの中に自分から課題を見つけ、他の人と協力しながら課題を解決しようとする学習です。もちろん、そのためには基礎となる知識や考える力が必要となりますが、これからは受け取る学習ではなく、積極的に学ぼうとする力が期待されるのです。
さあ、みんな、学びに行こう!





昨年度から本校で家庭科を担当しております
近藤 麻未 と申します。
本校は普通科の他に家政科(生活デザイン科)も設置しているため,家庭科教育にも特に力を注いでいます。
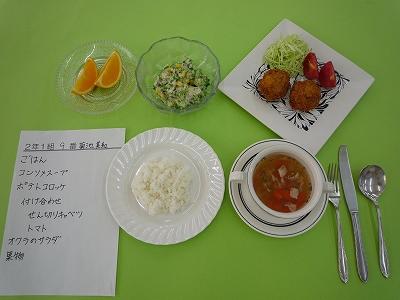
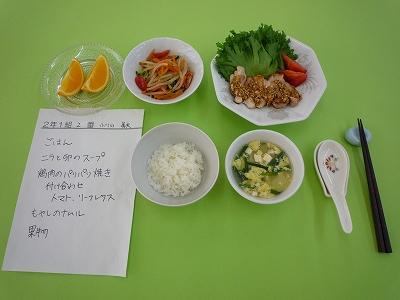
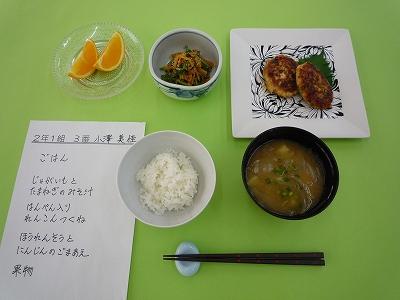
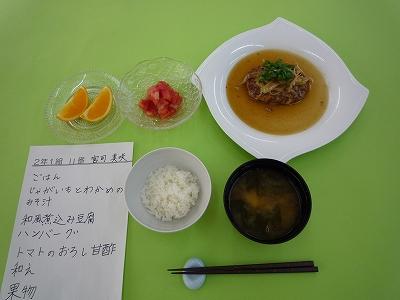



昨年度から本校で地理歴史科を担当しております 村舘 公大 と申します。
私は休日や夏季休暇を用いて,自転車で全国を旅しています。昨年は,石岡市から奈良県天理市まで(約600km)走りました。地理歴史科は自分の目で見て感じて気づく,そしてその土地の人とふれあい,その土地のものを食べることが大切な教科です。私は天理市までの道中でさまざまな経験をしました。東京から大阪まで“一人参勤交代”をしていた強者との出会いもありました。自転車は,車や新幹線に乗っていては気づかないことを気づかせてくれます。
自転車の旅での経験を話すと,生徒たちは笑って話を聞いてくれます。現地で見て学んだ,教科書には書かれていない話を生徒たちに伝えると,興味深そうにこちらを見てくれます。

こんにちは、この4月1日から図書館司書をしております大崎真弓と申します。






